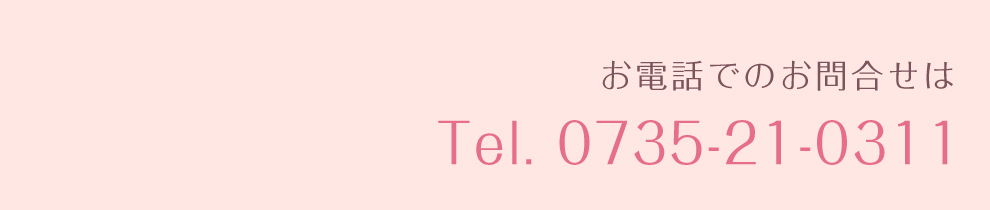無痛分娩は陣痛及び分娩時の痛みをとる方法で硬膜外麻酔を使用します。硬膜外麻酔とは脊髄を包んでいるクモ膜の外側にある硬膜外腔に管を通してそこから麻酔薬を投与する方法です。少量持続投与法を行うことにより安全に行う事が出来るようになりました。副作用としては血圧の低下、かゆみ、頭痛などがありますがそれぞれ対処可能です。分娩日を決めて行う計画分娩を行います。無痛分娩は分娩室にて経過を観察します。家族の方との面会、夫立会分娩も可能です。
はじめに
無痛分娩は希望者のみに行います。分娩日を決めて行う計画持続硬膜外無痛分娩となります。無痛分娩希望の方は後期母親学級に必ず参加していただき無痛分娩の概略を学んでいただきます。入院前には無痛分娩についてご家族の方同席のうえ詳しく説明し同意書をいただきます。
方法
分娩前日に入院していただき子宮頚管の準備状態により頚管拡張のための器具を当日に挿入します。硬膜外ブロックと呼ばれる麻酔方法を使用します。子宮収縮、子宮口の開大に伴う痛みは腰部の脊髄からの神経により支配され、その神経をブロックする方法を硬膜外ブロックといいます。まず背中を消毒剤で充分に消毒し、穿刺部位に局所麻酔を行ないます。硬膜外針といわれる特殊な針により穿刺後、細いチューブを硬膜外腔に留置して針を抜去します。その後薬剤を3mlずつ5分ごとに4回注入します。その間足が動くかどうか、耳鳴りがしないか、血圧は正常かなどを常に確認します。投与終了後氷のボールを使用して効果を確認し1時間に約10mlずつ持続投与を行います。その後陣痛促進剤により陣痛を誘発していきます。麻酔中常に足が動く事また耳鳴りがないかなどをお互いに確認していく事が重要です。もちろん血圧測定、状態の監視、お声かけを頻回に行います。これらにより後述の副作用を回避します。赤ちゃんの下降感、圧迫感は残存しますが、ほとんどの人は自然に近い形での分娩が可能です。しかし、まれに圧迫感なども除かれてしまい、陣痛自体が弱くなり、いきみに必要な力が不十分となる場合があります。このような場合は子宮底部を圧迫する事や、吸引分娩が必要になる事もあります。硬膜外カテーテルを利用することにより帝王切開も可能となります。
副作用
硬膜外ブロックにはいくつかの副作用があります。まずお母さんの血圧の低下が生じる場合があります。麻酔薬投与の前には絶飲食とし必ず点滴を行ないます。かゆみが起こる場合もありますが軽度です。硬膜外ブロックで重大な問題が起こることは非常に稀です。もし穿刺時に硬膜外腔の奥にある膜を傷つけてしまった場合頭痛を起こすことがありますが適切な治療を行うことにより回復します。もしそこへ麻酔薬が過量に投与されると呼吸筋にまで麻酔の効果がおよび、呼吸不全をきたすことがあります。これらの副作用は麻酔中に下肢の可動性を確認し、血圧を頻回に測定し、状態を監視することなどより十分事前に対処可能となります。また、麻酔薬が多量に脊髄周囲の血管内に入ってしまった場合、けいれんを起こすか更に稀なことではありますが呼吸循環不全を起こす場合があります。常に耳鳴りがないか口周囲に違和感がないか確認を行います。
その他
この麻酔法は穿刺という処置が必要であるため、脊椎に解剖学的異常がある場合、血液凝固障害のある場合、穿刺部付近の皮膚に感染がある場合、どうしても針が刺入できなかったりこの方法が嫌いだったり体位を取ることに協力してもらえない場合などは施行できません。陣発後に麻酔分娩を行わざるを得ない場合に脊椎麻酔と硬膜外麻酔を同時に行う脊髄硬膜外麻酔法を行うこともあります。この際には施行前に説明を行います。
おわりに
硬膜外無痛分娩の効果、注意点をよく理解いただき、慎重に施行することにより安全で快適な無痛分娩を目指します。
前日
母児の情報収集(既往歴,家族歴,妊娠経過)と助産録の作成。無痛分娩同意書と署名の有無確認。胎児監視装置の装着を行う。子宮頚管拡張器具(ダイラパン)の準備を行う。
当日
GE120㎖ その後胎児監視装置の装着。
硬膜外ブロックの実施
硬膜外ブロックの準備
消毒液 ポピドンヨード液、綿球、1%キシロカイン10㎖、10㎖シリンジ,硬膜外ブロックセット、2.5%ブピバカインの準備。ディスポーザブルマスクと帽子を装着する。
硬膜外ブロックの補助
血圧計の装着,500mlラクテック,ビクシリン1g点滴静注。側臥位に保持し硬膜外ブロックの補助、声掛けを行い不安の除去に努める。分割投与の際に血圧(2分ごとに測定)、呼吸、脈拍、下肢の可動、耳鳴りの有無、金属味の有無確認。硬膜外麻酔持続投与の準備。0.2%ロピバカイン25㎖、フェンタニル2㎖,生食25㎖を20㎖シリンジに準備する。
硬膜外部位ロックの開始
2.5%ブピバカイン3㎖を5分ごとに4回分割投与し効果を確認し以後持続投与を10㎖/hrで開始する。
陣痛促進剤の投与
5%グルコースにアトニン5単位を混注。12㎖/hrで開始し30分に12㎖/hrずつ増量する(有効陣通発来まで)。
硬膜外ブロック実施時
血圧(5分ごとに測定)、呼吸、脈拍、下肢の可動、耳鳴りの有無、金属味の有無確認。血圧、脈拍は自動記録計で記録を行うがその監視を行う。分娩担当者は原則分娩エリアから離れない(分娩室並びに授乳室、ナースセンター)、やむを得ず離れる場合は短時間としその間はナースコールの場所を再度教える、分娩監視装置を装着し連続監視する。 異常があれば医師に報告する。特に10分間に6回以上の陣痛があった時、レベル3以上の心拍異常が見られた時には速やかに報告する。少なくとも10分間に1回は母体、児の観察を行う。硬膜外麻酔施行時には半側臥位にし30分ごとに体位変換する。2時間ごとに導尿を行う。カテーテルの抜け、刺入部の出血の有無、点滴ルートの異常の有無を適宜確認する。痛みが出現したときには早めに医師に連絡する。(表情の観察も行う、声掛けも頻繁に行う)1時間ごとに内診を行い変化があれば連絡する。また2時間異常所見に変化がない場合も連絡を行う。
分娩時、分娩後のケア
分娩器具の準備
インファントウォーマー、保育器の準備。導尿、外陰部消毒並びに衛生材料の装着。
努責呼吸法の指導、誘導。児の観察、ケア、保温には十分に注意する。蘇生はNCPRに従う。臍帯血ガス、血糖値、ヘモグロビンを測定し記録する。母体の出血量を測定し子宮復古状態の観察を行う。分娩2時間後に医師による診察の後カテーテルを抜去する。
下肢の知覚回復状態の観察
下肢の知覚回復状態の観察を行い、歩行可能となるまで導尿を行う。第一歩行は付き添う。
出産後のケア
麻酔分娩体験の感想を注意深く受け止め正しい受け止めの手助けを行う。
| 分 娩 数 | 自然分娩 | 無痛分娩 | 帝王切開 | |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 平成22年 | 103 | 20 | 64 | 19 |
| 平成23年 | 169 | 50 | 95 | 24 |
| 平成24年 | 183 | 74 | 90 | 19 |
| 平成25年 | 231 | 87 | 114 | 30 |
| 平成26年 | 222 | 97 | 91 | 34 |
| 平成27年 | 287 | 124 | 122 | 41 |
| 平成28年 | 256 | 126 | 93 | 37 |
| 平成29年 | 243 | 125 | 78 | 40 |
| 平成30年 | 197 | 107 | 64 | 26 |
| 令和元年 | 144 | 89 | 38 | 17 |
| 令和2年 | 78 | 38 | 31 | 9 |
| 令和3年 | 145 | 83 | 47 | 15 |
| 令和4年 | 162 | 107 | 36 | 19 |
| 令和5年 | 109 | 53 | 42 | 14 |
| 令和6年 | 106 | 52 | 45 | 9 |
| 計 | 2638 | 1232(46.7%) | 1053(39.9%) | 353(13.4%) |
当院はJALA『無痛分娩関係学会・団体連絡協議会』ホームページにも掲載されています。
https://www.jalasite.org